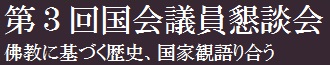大谷暢順台下のご講演から衆、参両議員等約20名が意見を交換する第3回国会議員懇談会が11月16日、参議院議員会館で開かれました。台下の講題は「円周の歴史 業(ごう)に動かされる国家、社会」=以下、全文掲載。「佛教に基づく歴史観、国家、社会観に目の覚める思い」「『御文』に『わが身のあさましきつみのふかきことをばうちすてて』がある。ご講義には仏様の教えが根底に流れており、自分自身もそう生きねばとの意を強くした」等、感銘の言葉が寄せられました。

台下のご講義を基に国会議員が闊達な意見交換
【大谷暢順台下のご講演】
「円周の歴史 業に動かされる国家、社会」
第三回国会議員懇談会を斯(か)くも大勢の御参加を得て開催できた事は、望外の喜びであります。この盛会にお力添えをいただいた、各先生方に感謝致します。
さて、昨年四月、私は『日本と日本人の明日のために』と題する本を出版致しましたが、それは今日我国を取巻く世界状勢が中々楽観を許さない問題に直面していて、この難関を切抜けるべく、我々は熟慮しなければならないと考えて、筆を執った次第です。
そこでですが、我々人間は青年時代に於て、銘々その後の人生をどう生きるべきか、種々(いろいろ)と考えを巡らせます。そして長い思索の後、青年には将来に向って一直線に伸びる理想の正義の道が定まります。
ところが豈図(あにはか)らんや中年になって、過去を振返って見て、「自分は若い頃期待していたのと、まるで違った人間になってしまったな」と述懐する人は結構多いのではないでしょうか?
八甲田山雪中行軍の悲劇
どうしてこういう事になるのか、―私は長い事、あれやこれやと考えました。「今更そんな事詮索するなんて随分暇人だな」と皆さん私を笑われるかも知れません。確かにその通りでしょう。―まあ、それは兎(と)も角(かく)、私はこの本を書いていまして、ふと思い出したのが、小学生時代に読んだ陸軍の八甲田山雪中行軍の話でした。皆様も御承知かとも思いますが、一応繰返しますと、日露戦争の直前、一ヶ連隊の軍隊が、吹雪の中を八甲田山登頂演習を実施しました。ところが途中で道に迷ってしまい、思案の末、少数の将兵を選び、救援を求めるべく、これに、軽装で山麓へ急行させる決定をしました。ところが、長時間待った揚句(あげく)、何とこの特命行動隊が、連隊の行軍列の最後尾に現れたというのです。つまりこの行動隊は、一直線に人里を目指した積(つも)りだったのに、目標物の全くない、真白な雪原の中を、大きく輪を描いて、元の出発点へ帰って来てしまったという謂(わけ)です。かくの如く人間は、生理的に一直線に前進できない者なのですね。
然(しか)し精神的には、人間は自由意志に基いて正義を目指して行動している。その道は未来に向って一直線に続いている―と一般的には考えられています。それでも実際には、青年時代に抱いた理想に到達した人は少ない―一体どうしてでしょうか? やはり精神的にも人間は将来に向って一直線に前進する事はできないのだ、と結論付けずにはいられないのではないでしょうか?
国家、社会にも及ぶ業力(ごうりき)
佛法では「人は各々固有の業(カルマン)を背負っている」と説きます。元々梵語のカルマンの訳として、この業(ギョウ)の漢字が当てられたのですが、佛語としてはゴウと言っています。これは人間の意志、行為、行動の総称です。
業(カルマン)という考え方は、人間の意志に基づく心身の働きを意味しますが、それが後に何らかの報いを招いて、又新しい業を作ります。業から業へ、それは連鎖を成して果(はて)しなく繋がって行きます。
更にそれは潜在的能力となって、過去から未来へ存続して、影響を及ぼし続ける力となるので、これを業力(ごうりき)と言います。
それ故(ゆえ)、人間は全く自由で、ただ思ったように生きればよい―と普通我々は考え勝(が)ちですが、実は容易にそれができない。何故かと言えば遠い遥かな昔から自らの造った業に操られて生死輪廻(しょうじりんね)を繰返しているのだからと佛法は説いています。
この「業」とか「業力」を佛法では一個人について説いているのですが、これを社会や国家に当て嵌めて、全く同様に考えられはしないか? 社会も国家も夫々(それぞれ)の自由意志に基いて正義の存在を続けていると自負しているが、実は、社会、国家自身が造った業に操られているに過ぎない。正義の道を直(ひた)走りに繁栄に向っているつもりであるが、何時(いつ)しかその道は衰退を始めている。個人も国家も、八甲田山雪中行軍のように、里へ向った筈(はず)の道程は一直線ではなく、繁栄から衰退へ円周の軌跡を踏んで原地点に戻ってしまう―こんな結論に私は達しました。
鎖国の江戸時代と文明開化の明治
そこで、我国の近現代史を考察してみますと、江戸幕府は天下統一を果したものの、ヨーロッパ諸国の日本植民地化の野望を見抜いて、鎖国令を発します。これによって武家政治が確立しますが、茲(ここ)に国家繁栄の道、即(すなわ)ちその業が造られたと考えてよかろうと思います。然(しか)しこうして我国が平和を享受している間に、西欧諸国は物質文明発達と共に、蒸気船を発明して、我国に来航する事となりました。
最早(もはや)、彼我の国力の差歴然たるものがありました。国家確立がそのまま滅亡の業に繋がった謂(わけ)です。つまり繁栄の一直線を辿った筈が八甲田山の例のように円周の軌道を描いて原時点に復(かえ)ってしまったと見ざるを得ないのではないでしょうか?
そこで我国は明治に入ると一路文明開化に邁進する事となります。これは明治維新を遂行した人々の熟慮に熟慮を重ねた後の政策転換、つまり、業の転換が行われて、これが日本を亡国の淵から救いました。即(すなわ)ち日本は危い鎖国の業から解き放たれた謂であります。
扨(さて)明治日本は文明開化をモットーに、上下(しょうか)力を併(あわ)せて国力増強に励み、やがて日清、日露両戦役に勝って、国土蚕食の虞(おそれ)を除くと共に、世界列強との平等条約を明治末年に締結するのに成功しました。こうして列強と対等の立場に立つという明治維新の目的は一応達せられた謂です。
ですから、その後我国は、国際的な対等性を一層確実にする為の将来に亙(わた)る長期的な外交政策を樹立すべきではなかったでしょうか?

文明開化で列強と並ぶ我国
ところが、幕末に黒船を差し向けて来た欧米諸国の中、英米両国とはその後我国は友好関係を保つ事に意を用いつつ、清国、ロシヤに対しては戦って、国土の安泰を得ました。然(しか)し日露戦争直後から、アメリカは暗に敵意を示し始めています。又第一次世界大戦後、革命によって成立したソヴィエト連邦も、徐々に反日的態度を濃厚にします。明治初年に清、露二大強国の脅威に直面して、これを退けるのに成功した我国は、五十年経過の後、又もや米ソ二大強国の脅威に直面する事となったのです。当(まさ)に正義の道は一直線ではなく、円周の軌道を描いて原地点に復った謂(わけ)です。つまりは幕末と同様の軍事、外交的危機が到来したのです。
然(しか)し乍(なが)ら、大正時代に入って、このように我国が又もや国難に見舞われ始めた事に対する国民の自覚はなく、それが最終的に昭和二十年の敗戦となり、国土は明治初年の版図(はんと)に縮まり、戦争放棄を誓約させられて、外敵の侵略には全く無防備な幕末の状態同様になりました。即ち文明開化は七十八年で円周の軌跡を画(えが)いて、原時点に復ってしまったのです。
人生にも国家にも必要な照顧脚下
国土の主要都市は皆焦土と化し、国民は日々の食にも欠ける塗炭(とたん)の苦しみに陷りました。然(しか)しその中で日本人は再奮起して、只管(ひたすら)生業(なりわい)に励み、十年足らずで経済を建て直し、やがて日本は諸外国が目を見張る世界第二の経済大国となる大発展を遂げました。我国の歴史上未だ曽(かつ)て経験した事のない大繁栄に恵まれたのです。
このように日本の近現代史を振返ってみると、三回に亙って、亡国の危難に直面しながらその度(たび)にこれを切抜けて、却(かえ)って繁栄の道を見出した謂で、一応我々はこの歴史的事実を誇(ほこり)としてよいかと思います。
かかる艱難(かんなん)を切抜けるには、大へん辛い事ではあるが、勇を鼓(こ)して一旦立止って、徒(いたず)らに正義感に逸(はや)る事なく熟考する事が肝心でしょう。それは個人なら個人、国家なら国家が自らの業が何であるか深く見極める事とそれの間違いに気付いたならば、速かに潔くこれを改める事です。
照顧脚下(しょうこきゃっか)(脚下(あしもと)を照し顧(かえりみ)る)という言葉がありますが、これは一国の歴史でも、一人間の生涯の中でも、折に触れて必ず為されなければならない必要欠くべからざる心懸けでありましょう。
唯(ただ)敢えて言えば、三度目の、つまり昭和二十年の終戦の決断は相当遅きに失した悔(くや)みの残るところです。
そこで我国は今後どのように運営されるべきか、熟慮しなければならない時が来ていると私は感じます。正義の道は決して真直(まっすぐ)に将来に向って伸びていない事は、この昭和二十年の敗戦で、我々は充分に知らしめられた筈です。とは言え過去に標榜された正義の道が間違っていたのだから、今度はその正反対の道―即(すなわ)ち国家も国民も唯(ただ)経済に専念していればよいという短絡的な考え方はより一層危険であります。
事実、年号の昭和から平成に移る頃から日本経済に翳(かげり)が見え始めます。加之(しかのみならず)、とても経済だけ考えてはいられない時代になってきました。目下(もっか)近隣諸国が、お互いに競い合って次々と我国に不当な難題を持ち掛けて来ています。丁度(ちょうど)幕末、アメリカ、ロシヤ、イギリス等が代る代る黒船で日本の港に押し入って来た状況に酷似しているではありませんか。
幕末と酷似 現代の外交危機
幕末の時点では、欧米列強の強圧を受けて、開国を、それも我国にとってこの上なく不平等で屈辱的な通商条約を締結しなければなりませんでしたが、現在は近隣諸国から、同じく不平等且(か)つ屈辱的な政治関係を押し付けられて来ています。 繰り返しになりますが江戸幕府も、明治政府も、只管(ひたすら)国家繁栄の大道を驀進(ばくしん)したのでしたが、進路が何時(いつ)しか湾曲を始めて国家衰退の逆方向に向いていました。 但し、幕末、明治の人々は、その時照顧脚下する叡智に恵まれていた。それに反し、大正初期から第一次世界大戦後頃の日本人はこの叡智に欠けていたと考えざるを得ますまい。 而(しか)らば目下の我々は、国家の業と業の連鎖が起す業力が知らぬ間に逆方向へ動き始めている事に、一日も早く気付くべきです。 一つの業は次に新しい業を産んで連鎖状に繋がるのですが、その一つ一つの業は決して同じ物ではありません。つまり一個人にしても、社会国家にしても、又世界全体にしても、それ等各々は各々の業力に動かされて、押し流されて、知らぬ間に思いもかけない方角に変容して行くのだという事を強く意識して置くべきです。

新たな業を生んだ黒船来航
昭和二十一年に現行憲法が発布されたのは、第二次世界大戦後僅(わず)か一年しか経て居らず、世界中の殆(ほとん)どの人々がすっかり戦争に倦(う)み、もう二度とこういう悲惨な事態は起って欲しくないと考えていました。それにアメリカとソ連、二大強国が略(ほぼ)勢力均衡して対峙していて、爾(じ)後(ご)半永久的に世界平和が続くであろうという安易な楽観論がかなり浸透していました。
然(しか)しもうこの二大勢力均衡の構図は潰(かい)滅(めつ)して久しく、又強大な破壊力を持つ多数の新兵器の登場で、世界状勢は全く危険極まりない様相を呈するに至っています。
目下日本国家の運命は、幕末或(ある)いは終戦時の状勢に円周の軌道を踏んで舞い戻って来ているという認識が必要です。否(いな)、その危険度は幕末、終戦の時点を上回るものという気が致します。
業の変化に気付くべし
敗戦の結果、その後は非武装の国として経済の再建、発展にのみ専念する平和国家として生れ変るのだという国民意識の転換は、昭和二十年の時点としては、必ずしも誤りではなかったかも知れません。それがその当時日本国民に課せられた業でもありました。そして実際その後三、四十年で科学、経済は長足(ちょうそく)の進歩を遂げて、万年貧乏国と考えられて来た二千数百年の日本の歴史、国家の後進性を一気に払拭して、今や国民生活の利便さは世界一となったのですから、これは自ら多とすべきでしょう。
然(しか)し目下世界状勢は一変しました。日本と日本国民に課せられた業が変ったと早く気付くべきです。歩んできた歴史の道が円周の軌道を踏んで、終戦当時の時点に戻って来ているのです。
北朝鮮は数百名の邦人を拉致したまま、数十年に亙(わた)って、この不幸な人々を我国へ帰還させない儘(まま)です。幕末の黒船来航の折にも、我国はこれ程の災難には遭いませんでした。
ところで昭和二十年には、已(すで)にポツダム宣言を受諾した後、即(すなわ)ち戦闘状態は終了しているにも拘らず、ソヴィエト連邦は大陸にある数十万の日本軍民を極寒のシベリヤへ拉致し、強制労働の果、数限りない人々を死に至らしめました。
北朝鮮はこういう非道行為は許されるとソ連から学んだのだと思います。ですからよくよく考えてみれば終戦によって、日本と日本国民に本当の平和が訪れた謂(わけ)ではなかったのです。我国は完全な独立、自由を認められているとは言えないではありませんか?
更に韓国は竹島を占領し、中華人民共和国は尖閣列島侵略を画策しています。又ロシヤは我国の北方領土に何時迄(いつまで)も居坐っています。
憲法九条改正を急げ
戦後七十四年で日本の進路は円周の軌跡を踏んで原時点に戻って来たと申しましたが、実は日本も日本人も昭和二十年以来完全には平和でも安泰でもないのです。ソ連と北朝鮮に続いて、今後第三の邦人拉致・抑留が起らないという補償はありましょうか?
正にこの年に当って、中華人民共和国の生物兵器との疑いもかけられる武漢ウイルスが襲来しました。これは何かの暗示ではないかと私には思われてなりません。ですから今当(まさ)に国民挙げて智恵を集めて、熟考深慮、照顧脚下して、今後の新たな日本の進路を定めなければならない時機が来ています。
今や、久しく懸案となっている現行憲法九条の見直しは実に急務でありましょう。この九条改正なしに、北朝鮮拉致抑留の邦人解放の道が開けて来るとは、どうしても私には考えられません。そしてそれと同時に日本の将来進むべき道を、国民挙げて真剣に討議しなければなるまいと愚考するところであります。
長時間の御清聴、有難うございました。