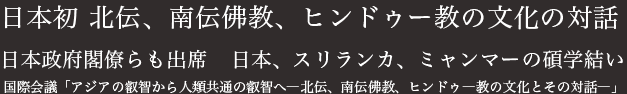本願寺維持財団(当時:現一般財団法人本願寺文化興隆財団)では平成22年10月23、24の両日、国際会議「アジア文化会議 京都」を東本願寺東山浄苑で開催しました。北伝、南伝の両佛教、ヒンドゥー教の宗教、文化を論じる世界初の会議で、テーマは「アジアの叡智から人類共通の叡智へ―北伝、南伝佛教、ヒンドゥ―教の文化とその対話―」。その文化的意義の高さからスリランカ政府、ミャンマー連邦大使館の共催、外務省、文化庁、京都市、国際交流基金や比叡山延暦寺、曹洞宗、日蓮宗らわが国の主要教団と宗門大学の協力、後援を得ました。会議では前原誠司外務大臣(当時)、福山哲郎内閣官房副長官、門川大作京都市長のほか、マヒンダ・ラージャパクシャスリランカ大統領(代理)やミャンマー宗教大臣(代理)が出席。大谷暢順理事長が基調講演をしたほか、日本、スリランカ、ミャンマーの碩学が意見発表し、そのもようが各紙に報じられました=別掲。

- 「アジアの叡智を世界へ」と論じ合ったシンポ
基調講演 大谷暢順理事長
日本佛教は、西暦六世紀に公伝して以来の佛教と、約六百年の星霜(せいそう)を経て誕生した鎌倉佛教とでは、歴然たる差違が認められると思うのですが、それは末法(まっぽう)思想というものヽ出現によると言えましょう。たヾ、世の中が末法時代に入ったからと言って、そこに何ら科学的根據(こんきょ)は存在しないのですが、民心(みんしん)にかなりの動揺が起りました。そして、末法の世に生きているという意識を、現代の我々も持ち続けています。
鎌倉幕府の成立は一一九二年で、末法時が始まったとされるのは、その百年以上前の、一〇五二年です。その百年の間に、貴族階級は徐々に力を失い、政治権力は武家の手に移ります。こうした社会の変遷は、当時の人々に、末法の時代に入ったという実感を与えました。そしてそういう世の中の儚(はかな)さに、救いを齎(もたら)すものとして、鎌倉佛教が登場するのです。ですから、末法の世に今もあると信じられている限り、現代人も鎌倉佛教を信頼し続ける事になるのでしょう。
末法時に入ると、もう誰一人、覚(さとり)を開けなくなる、それどころか、佛道修行さえもしなくなるのだ、と言われています。それは即ち末法には、それ以前の時代より、人間の機(き)根(こん)(能力)が低下するという事です。けれども、そうだからと言って、凡(すべ)ての人間が、且(かつ)ては覚を開けたというのではありません。それは、言い換えれば、昔は賢者も愚者もいた。それに反して、末法時には、誰も彼(か)も無能力になってしまっている。この教えは、本来、悲観主義、敗北主義思想であった筈です。それが、思いもかけず、一種の平等思想を醸成(じょうせい)する事となった、と私は考えるのです。
果して、新しい宗旨の開祖達は、口を揃えて、佛の教えは、あらゆる人々の為にあるのだし、又(また)そうでなければならないと主張しました。鎌倉諸宗派が、大成功を収めた一因はこヽにあったのです。
末法時の始まりと、武士階級の抬頭(たいとう)とは、不思議な事に、時を同じゅうしていました。その頃我国は、三千以上の荘園に細分されており、その大部分が不輸(ふゆ)不入(ふにゅう)の特権を有し、京・奈良の大寺院や権門(けんもん)勢家(せいけ)の所有となっていました。一方、地方の有力者達は、荘園内の大名主などを配下に組み込んで、徐々に力をつけ、それ<の地方に、武士の集団が誕生しました。
地方武士団は次第に強力となって行きますが、この新興階級にとって、やはり精神的支柱とでも言うべきものが必要となって来ました。
武士の集団であるからには、当然「規律」がなければならないが、戒律を忠実に守ろうとする禪の教えは、当(まさ)にその要請に合致するものでした。精神鍛錬をせねばならぬ武士には、禪の坐禪(ざせん)修行は最適でした。臨済の榮(よう)西(さい)、曹洞の道元(どうげん)等は、武士階級から大いに歓迎されたわけです。
浄土門の教えにとっては、戒律に対する考え方は、全く違って、それは不必要であるという立場を取りました。親鸞は、それどころか、戒律を守ろうと努めるのは、阿弥陀佛の救いに頼り切る気持を妨げるので、かえって好ましくないと主張しました。
けれども、浄土宗の方は、曹洞と同じく、地方武士社会にかなり浸透するようになります。臨済の方は、それに反して、中央の武家の棟梁に迎えられるようになります。侍というものは、屡々(しばしば)人の命を奪わなければならない、つまり殺生(せっしょう)戒(かい)を犯すのを余儀なくされますが、阿弥陀如来の慈悲にひたすら縋(すが)るならば、如何(いか)に罪は重くとも、必ず救われるという浄土門の教えも、禪とは又違った意味で、強く武士の心を魅きつけたのであります。
然(しか)し鎌倉佛教の他の宗旨よりも、末法という考え方に、一層強く根ざしていたと思われる、法然、親鸞など浄土門の人々は、厳しい修行を勧める釈尊の教えを、今の人々はもはや遵守する能力がなくなったのだと言って、武士よりも低い身分の民衆に教えを弘めたかったわけです。彼等こそ、最も素直に、如何に愚かで罪深い者も救おうという阿弥陀佛の教えを聞き入れるであろうと考えたからです。
ところが、浄土教の民衆への伝道は、それ程易(やさ)しいものではありませんでした。当時は文化の後進地帯であった東国では、民衆はその日暮しに追われて、魂の救済を考えるゆとりはあまりなかったようです。彼等より、生活が少しましになっていた都を取巻く畿内地方の荘園農民達は、一方で荘園領主、他方で守護・地頭の苛斂誅求(かれんちゅうきゅう)に対応するのに忙しく、未だ来世を考えるところまでは行っていませんでした。
鎌倉佛教の榮光(えいこう)は、今日も尚引継がれているようです。それは、この時代に、佛教が民衆の間に弘まった、と思われているからでしょう。けれども実際は、それ程速く伝播(でんぱ)したわけではありません。
然(しか)し乍(なが)ら、鎌倉佛教の諸宗は、民衆の覚醒(せい)を促したという点で、言而(いわば)レジスタンス(抵抗)的性格を帯びていたと言う事ができましょう。これは、後の室町、戦国時代になって、蓮如が多数の農民門徒を糾合(きゅうごう)した浄土真宗教団の確立に成功する事となり、又(また)日蓮宗諸派の聯合(れんごう)体による京の町衆(ブールジョワ)の組織ができ上る道を開くのであります。
浄土教の諸師は、国民の大部分が文盲(もんもう)であった時代に、阿弥陀佛の救いは、一文(いちもん)不通(ふつう)の人々に向けられたものである事を強調しましたが、鎌倉佛教は、そういう意味で、一つの「啓蒙」運動であったという事もできるのです。禪宗諸派の方はどうかと言いますと、こちらは日本文化の形成に大いに寄与しました。華道、茶道、武道などに、明瞭に禪の影響を見る事ができます。
旧来の佛教諸宗は、言う迄もなく、鎌倉の新佛教には敵対的でした。鎌倉・室町両時代を通じて、旧佛教側から執拗な弾圧が行われました。朝廷に訴えたり、武家の力を借りたり、又彼等自身の養っていた僧兵を動員したりして。こういう事から、鎌倉佛教は、時折、西洋史上に有名な宗教改革に比較されます。
然しこの連想は、あまり適当とは思われません。我国の場合は、寺院が毀(こわ)されたとか、焼き拂(はら)われたとか、いざこざの間に死傷者が出たとか、高僧達が島流しになったとかいう程度の弾圧で終っています。西洋で、宗教改革・宗教戦争、そして又異端(いたん)訖(きっ)問(もん)裁判などで為(な)された惨(むご)たらしい数々の事件とは、まるで性格を異にするものです。鎌倉新佛教の殉教(じゅんきょう)に讃辞を惜しまない歴史家や佛教界の人々は少くありません。けれどもそれは、至って平和で穏やかだった日本史の中でのみ語り得るものでしょう。
鎌倉幕府成立は、然(しか)し乍(なが)ら、日本史上の一大転換期でした。社会構造の変貌(へんぼう)は相当酷(きび)しいものでした。然し破局的なものにはなっていません。たヾこの事が、「個」の自覚を喚(よ)び起したように、私には感じられます。
鎌倉佛教の榮光(えいこう)は、今日も尚引継がれているようです。それは、この時代に、佛教が民衆の間に弘まった、と思われているからでしょう。けれども実際は、それ程速く伝播(でんぱ)したわけではありません。
然(しか)し乍(なが)ら、鎌倉佛教の諸宗は、民衆の覚醒(せい)を促したという点で、言而(いわば)レジスタンス(抵抗)的性格を帯びていたと言う事ができましょう。これは、後の室町、戦国時代になって、蓮如が多数の農民門徒を糾合(きゅうごう)した浄土真宗教団の確立に成功する事となり、又(また)日蓮宗諸派の聯合(れんごう)体による京の町衆(ブールジョワ)の組織ができ上る道を開くのであります。
浄土教の諸師は、国民の大部分が文盲(もんもう)であった時代に、阿弥陀佛の救いは、一文(いちもん)不通(ふつう)の人々に向けられたものである事を強調しましたが、鎌倉佛教は、そういう意味で、一つの「啓蒙」運動であったという事もできるのです。禪宗諸派の方はどうかと言いますと、こちらは日本文化の形成に大いに寄与しました。華道、茶道、武道などに、明瞭に禪の影響を見る事ができます。
旧来の佛教諸宗は、言う迄もなく、鎌倉の新佛教には敵対的でした。鎌倉・室町両時代を通じて、旧佛教側から執拗な弾圧が行われました。朝廷に訴えたり、武家の力を借りたり、又彼等自身の養っていた僧兵を動員したりして。こういう事から、鎌倉佛教は、時折、西洋史上に有名な宗教改革に比較されます。
然しこの連想は、あまり適当とは思われません。我国の場合は、寺院が毀(こわ)されたとか、焼き拂(はら)われたとか、いざこざの間に死傷者が出たとか、高僧達が島流しになったとかいう程度の弾圧で終っています。西洋で、宗教改革・宗教戦争、そして又異端(いたん)訖(きっ)問(もん)裁判などで為(な)された惨(むご)たらしい数々の事件とは、まるで性格を異にするものです。鎌倉新佛教の殉教(じゅんきょう)に讃辞を惜しまない歴史家や佛教界の人々は少くありません。けれどもそれは、至って平和で穏やかだった日本史の中でのみ語り得るものでしょう。
鎌倉幕府成立は、然(しか)し乍(なが)ら、日本史上の一大転換期でした。社会構造の変貌(へんぼう)は相当酷(きび)しいものでした。然し破局的なものにはなっていません。たヾこの事が、「個」の自覚を喚(よ)び起したように、私には感じられます。
先ず禪は、教祖釈尊(しゃくそん)が教えた通りの佛教の原点に復ろうとします。それは禪の開祖達、特に道元にとっては、精神の統一、禪(ぜん)定(じょう)を結ぶ事だったのです。
末法の世に生きているという気持の最も強かったのは、浄土門の師達でしたが、彼等にとって、末法の人々を救い得るのは阿弥陀佛以外になかったわけで、我々はたヾ念佛に励むだけでよかったのです。
日蓮は法華経が釈尊の真意を伝える唯一の経典だと宣言しました。
以上三群の宗旨は、夫々(それぞれ)の道に於(おい)て、教義の単一化を模索しました。これはその時代の要請でもあったのです。個人の救(すくい)を求めるという意味に於(おい)て、言而(いわば)教えの純粋化の希求(ききゅう)だったと言えるでしょう。(西洋の宗教改革で、イギリスの新教徒がピューリタンと呼ばれた事を連想してみて下さい)。新佛教が求めたもう一つの要素は単純性でした。民衆に受容れられ易い為にです。
日蓮は一切(いっさい)経の中で、たヾ法華経のみを選びましたが、決してこの経の読誦(どくじゅ)を奨めたのではなく、お経の題名を「南無妙法蓮華経」と、ひたすら、繰返し唱えるように提唱したのです。これを「七字の題目」と言いますが、何か南無阿弥陀佛を六字の名号と言うのを模した感があります。この名号を称(とな)える事を奨めた浄土門の方も、教えを単純簡明にしたと言えます。元来「念佛」には、文字通り「佛を念ずる」、思いをこらして、阿弥陀佛の姿を心に思い浮べる―観想(かんそう)念佛という教えもあったのですが、法然以後、それを全く廃して、たヾ口で「南無阿弥陀佛」と言う「称名(しょうみょう)念佛」のみが説かれるようになったのです。
釈尊入滅よりこの頃まで、已(すで)に千七百年の時が経っているのです。そしてその間、佛教は殆(ほとん)どアジア全域に弘(ひろ)まり、様々な国々、様々な時代に於(おい)て多数の宗旨に分れました。そこでその中のかなりの教えが日本に伝播しています。それは実に多種多様でしたけれども、我々の祖先は、そこに或(ある)種(しゅ)の統一性を作り上げるのに成功しました。
未曾有(みぞう)の大佛・大日如来の鋳造(ちゅうぞう)と、奈良東大寺の建立、地方の国毎に国分寺、国分尼寺を置いたのがそれで、こうして佛教は我国の国教となりました。当時、都の奈良には六つの宗旨がありました。薬師佛、阿弥陀佛、弥勒菩薩、地蔵菩薩などが、大日如来と共に奉安されて、日本人は別段それが不都合だとも思わず、国民全体が佛教徒として生活したのです。多様性の中に統一を保った、鎮護国家思想の教えに生きたのです。
ところが武士階級の抬頭は、社会秩序に動揺を来(きた)しました。国の統一性は失われ、朝廷と幕府の間には、鎌倉時代を通じ、更(さら)に後の時代に亘って 潜在的対立を続けるのです。
佛教界も亦(また)決定的な変貌を遂げる事となります。どちらかと言うと、それまで現世の幸福を説いていた佛教に、人々は飽き足らなくなり、「あの世」という事に関心が向けられ始めます。社会全体の幸福を祈るという事よりも、個人々々の救済を願う事を考えるようになったのです。つまり「個」に目覚め始めたと言えましょうか?
鎌倉佛教祖師達は、佛典を真剣に学び始めました。然しそれ等を佛教学として学ぶのではなく、人間の魂の救いの道をそこに見出そうとしたのです。彼等は数百巻の一切(いっさい)経(きょう)の中に埋没して、それ等が屡々(しばしば)お互いに矛盾しているのに当惑もしたでしょう。学問に学問を重ね、又苦渋に充ちた熟考・反省の揚句(あげく)、人間の救いへの渇望に応え得るたヾ一つの述作、時にはたヾの一行につき当るまで苦悶し続けました。
彼等は、そこで、これこそと確信した経典或いは論釈の一箇所に、言而(いわば)白羽の矢を立てヽ、佛教の他の教説を、大胆にも残らず捨てヽしまったのです。
榮西、法然、親鸞、道元、日蓮等の宗旨はこうして誕生しました。それ等は千七百年間に培われた佛教の教説―中には非佛教的な要素も、夫々(それぞれ)の地方の土着信仰も、(それには、日本の物もあれば、外国の物のあります)そういうありとあらゆる物が混在した尨(ぼう)大(だい)な宗教文化の継承体、そこから「捨象(しゃしょう)」に次ぐ「捨象」の作業を経た後にでき上ったものなのです。
この傾向は、時代を経る程先鋭となって行きます。法然より親鸞が、榮西より道元が、一層断定的であります。改革者達は、こうして、民衆の魂に触れると思われる教理を立てて、他の一切を投げ捨てたのです。
鎌倉佛教の確立は、従って、一口に言って、求心力の作用であると私は思います。この求心性のエネルギーは、鎌倉の後も、南北朝、室町を通じて、愈々(いよいよ)その勢力を増して、戦国時代になって、その頂点に達します。
これに引き換え、古来の佛教では、教説はまち<でした。けれども、宗旨相互の間では、大した摩擦もなく、融和した統一性が保たれ、而(しか)も大いに活気もありました。それで私は、そこに遠心力が作用していたのだと思うのです。
以上、鎌倉佛教と、それ以前の佛教について鳥瞰(ちょうかん)的に眺めて参りました。そこで、この両者間の大きな違いに御注目いたヾきたいと思います。旧来の佛教は、その多様性にも拘らず、互いに融合し合っていました。それに反し、鎌倉佛教は、それ<の宗旨の教理としては 単一性を持つようになったが、各宗相互間は極めて非妥協的となったという事です。
日本佛教史中でのこういう対称的なあり方は、今日の我々にとって、興味深く、又これを他山の石として、今後の佛教界の為に、大いに参考にすべきかと私は思います。鎌倉佛教は、現世の幸福とか、道徳とかいう事ではなく、教えを自己自身のものとして考える、或(ある)意味で、人間性の確立を成し遂げたという大きな功績があったと言えましょう。又一面、佛教を一般民衆に弘めようとした、今日的な表現をすれば、あらゆる人々に開放しようとした、というのも賞讃すべき事だと思います。
そこでその教説は、単純明解なものとなり、純粋一途なものとなりました。佛教はそこで、教義上の大変革、大発展を遂げた―今日の人々は概ねこのように鎌倉佛教を認識しているように私は思います。
明治以後、所謂(いわゆる)新興宗教が続々と誕生し、その傾向は今日も続いていますが、これ等も新しいとは言いながら、鎌倉佛教精神とでも言うべきものを、肯定し、継承しているように、私には見えるのです。
他方平安時代以前の佛教は、鎌倉佛教から見れば、教義的に未発達のように看做(かんか)されるかも知れませんが、それが国民全体の精神的支柱になっていた事は間違いありません。佛教によって国全体が融和統一を保っていたのです。
そして教えとしては、小乗佛教あり、大乗佛教あり、密教あり顕(けん)教(ぎょう)ありで、拝まれる佛も、様々であった事は、前にも述べた通りですが、その為に大きな争(あらそい)の生じた事はなく、それに在来の我国の神々にも、本地(ほんじ)垂迹(すいじゃく)という考えによって、同様に崇(あが)められる有様で、今日の我々から見れば、実に雑然たる言而(いわば)寄合世帯だったのですが、然しその中で、誰もが皆佛教徒であるという自覚に生きていたのは、注目すべきではないでしょうか?
鎌倉佛教について、私は「求心力」と申しましたが、平安以前の佛教では、逆に遠心性がエネルギーとなって、佛教の繁榮が齎(もたら)された、という風に私は感じるのです。
さて、今の世の中で、我々は単に鎌倉佛教を継承し続けているのみでよいのでしょうか?それ以来、已に八百年以上も経過した今日、当初それ程新鮮であった教義は、もはやその精彩を保ち続けていません。何故でしょう?
先ず文盲のなくなった現代、「啓蒙」の意義も亦(また)なくなっています。又貴族階級、武士階級も過去の存在となって、もうレジスタンスの対象もありません。又情報社会の世の中となって、(良し悪しの問題は別として)人間の個性は急速に影がうすくなって来ています。
先程から枚擧(まいきょ)致しました、鎌倉佛教の幾つかの特質は、今やその受容(うけいれ)基盤を失っていると私は感じるのです。つまりその存在理由(レゾンデートル)がなくなってはいないでしょうか?
鎌倉佛教が求めた純粋化、単一化は、教団が物心両面で、時代を経て硬化して来ると共に、排他主義の傾向に堕して来たきらいがあります。
今茲(ここ)に、明日の佛教という事を考えますと、やはり鎌倉佛教の形骸を、我々は何時迄も引摺(ず)って行くべきではないような気がします。
抑々(そもそも)鎌倉佛教というのは、その前時代の佛教を否定して出現したと考えられますが、これをヘーゲルの弁証法に当て嵌(は)めれば、アンティテーゼの佛教であります。私は今やそのジンテーゼを立てるべき時に来ていると思います。
一切衆生(しゅじょう)が救われるのが佛の道であるという事、それは我々各々の心の問題であって、単に、死者の霊を弔うとか、世の中全体の幸福を願うとか、そういう自己を離れた問題ではない事を明らかにした点で、鎌倉佛教の功績は大きいと思います。確かに我々は銘々、自分の信仰を持つべきでしょう。
然しそうした上で、我々は他の宗旨や宗教をも認める寛容さを備えなければなりません。様々の教説が行われていながら、お互いの間に、反撥(はんぱつ)・抗争を起さなかった奈良平安以前の佛教には、そういう点で学ぶべきものがあります。この両佛教の合(ごう)定立(ていりつ)(ジンテーゼ)を求めて行くのが、今後の国際社会に向って、我々佛教徒の取るべき態度ではないかと、私は考えます。