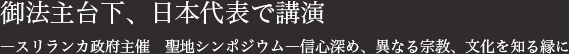大谷暢順御法主台下が一月十二日、スリランカ政府主催の国際シンポジウムに日本代表として招かれ、その名代に霊光院大谷実成御連枝殿を派遣されました。会議のテーマは、「聖地の果たす役割 宗教と文化の相互理解」。スリランカ、インド、ネパールの大臣、政府高官、学者ら約五百人が見守る中、霊光院御連枝殿は台下から託された記念品をマヒンダ・ラージャパクシャ・スリランカ大統領へ贈呈し、日本語と英語で台下の講演を代読されました。

- 台下の講演(代読)に聞き入る
スリランカ、インド、ネパールの大臣、学者ら
まずは、この国際会議に日本代表として発表する機会を与えて下さったスリランカ政府に感謝します。
さて、現在、日本には自然遺産三件、文化遺産十一件、計十四件の世界遺産があります。私たちの本願寺がある古都・京都の一部の神社仏閣等も1998年、文化遺産としてユネスコに登録されました。
世界遺産の認定は、世界各地で同様の現象を引き起こしているように正と負の効果をもたらします。京都も例外ではなく、日本国内外より多くの観光客が京都に押し寄せ、様々な経済効果を地元に与える一方、景観、環境の破壊や、その根幹を成す宗教、精神文化への理解不足から生じる問題なども生じています。
今回の会議のテーマにあるように、世界遺産を含めた聖地の保存、称揚(しょうよう)と経済開発の関係は、互いに平行線を辿り、容易に相容(あいい)れない現実を抱えています。
その一つとして、これらの世界遺産を含めた聖地を訪れる人々の興味の対象は、せいぐ歴史、芸術、文学等の領域を出でず、その基底を成した佛教や神道に対する無関心、即ちこれ等遺産が我々の祖先を育んだ信心の結実である事を失念してしまっています。佛像の前に出ても礼拝どころか、被(かぶ)っている帽子すら取らず、歴史的遺産、あるいは、芸術・美術品の類として観賞する人が少くありません。また、日本の多くの経済人、政治家、官僚たちも聖地をいかに経済活用するかだけを重要視している嫌いがあります。
誠に嘆かわしく、残念な現実でありますが、この精神的混迷を招いたのは、明治期以降の日本が目的と手段を混同し、はき違えたことによるものと言えましょう。国家の目的とは何か。明治維新ではヨーロッパ列強による植民地化を防ぐべく、富国強兵を敢行しました。しかし、強大な軍事力を持つことは、元来目的ではありませんでした。真の目的は、西洋諸国に伍(ご)して政治と外交を行い、日本の精神、文化を昂揚することによって国民の生活を豊かにすることだったはずです。次に第二次大戦後の荒廃の中、日本は経済発展による国の復興を第一義としました。これも国が生きてゆくための手段であり、目的ではありませんでした。にも拘(かかわ)らず、今日に至っても尚(なお)経済力を高めることにのみ腐心し、伝統の宗教、文化の興隆の勤めを忘れ、国家の政道は立たず、国民は心の拠所に迷い続けています。
また、GHQの政教分離によって、宗教をあらゆる場から排除、抹殺せんとする風潮が蔓延(まんえん)しているのも、日本人の精神的混迷を築いた要因であります。分離とは、暗に一方が他方を軽蔑し排斥することになっています。
教育の現場でも宗教が極端に排除された結果、海外で自分は無宗教と公言し、却って冷笑される日本人が少なくないようです。GHQによって押しつけられたとは言え、「政教分離」について、未だに無批判であってよいものでしょうか。

- スリランカ政府認定聖地となった津波本願寺佛舎
(本願寺維持財団(当時:現一般財団法人本願寺文化興隆財団)寄進・スリランカヒッカドゥワ)
私は数年前、京都の世界遺産・銀閣寺に隣接する半鐘(はんしょう)山の乱開発に対して、反対する地元住民の友人から相談を受けました。半鐘山は銀閣寺から僅か数百メートルの所にある小さな丘陵地で、京都市が定めた古都保存法により、開発を制限する歴史的風土保存地区とされています。
しかし、無責任な宅地造成によって、樹木が伐採され、山肌が削られるという無惨な姿に変容し、銀閣寺を含めた世界遺産一帯の景観が破壊される危機を迎えたのです。
住民たちは建築確認を認めた所轄官庁に不服を申し出ましたが、私は地元行政への批判だけではなく、視点を世界に向けるべきであると忠告し、自らフランスへ赴いて、パリーのユネスコ本部へこの窮状を訴え出たところ、大いに理解を得る事ができました。速刻ユネスコから我国政府へ照会があった模様で、事態は急速に好転し、半鐘山開発計画は中断となり、惨禍(さんか)を未然に防止できたのです。
抑半鐘山一帯は、世界遺産に指定された銀閣寺に隣接しているというので、その準保存区域(ゾーヌ・タンポン、バッファーゾーン)なのですが、それが却って建設業者の開発意欲をそゝる事になってしまったのです。つまり「銀閣寺の近くに住居を構えられますよ」という歌い文句が、分譲の宣伝に使われました。
こういう次第ですから、私は今後『世界遺産』という問題を、世界の国々も、国民も、もっと真剣に考えるべきだと思います。特に文化遺産は我々の先達の信仰心によって産み出されたものであり、多大なる苦難の末、彼等の智惠(ちえ)と努力の凝縮の賜物(たまもの)である事に深く心を致さねばならぬと思うのです。苟(いやしく)も尊い世界遺産を以て、観光資源として利用しようなどという軽佻浮薄(けいちょうふはく)なる態度は嚴(げん)に謹むべきでありましょう。
このように、聖地の保存とその開発の問題は、ともすれば経済を優先する傾向が否(いな)めません。今回、日本の例を出してその危機に警鐘を鳴らしましたが、先ずは聖地の問題を含めた宗教、精神文化に対する国民の意識の昂揚を図ることが重要であります。
そこで、私たち本願寺維持財団(当時:現一般財団法人本願寺文化興隆財団)は佛教に基づく日本人の精神と文化の復興、さらには、人類普遍の文化の発展に資するべく、国内外で活動を続けています。
今の日本人にとって最も必要なのは、信心の回復です。傲慢ではなく、あくまでも謙虚な心をもって佛教徒として、日本人として、矜持(きょうじ)を持つ。私はこれこそが日本を救い、ひいては、世界の再生につながると確信し、運動を続けて参りました。その結果、日本をはじめ、スリランカやフランスなど海外からも賛同と理解の声が寄せられています。
世界の聖地の大部分が、根元を宗教に持ち、神佛への崇敬の心がそれを築き上げたのです。聖地と同じ信仰を持つ人はそこに参拝することによって信心を深め、引いては歴史や文化を学ぶ機縁とする。また、異なる信仰を持つ人には、それが違う宗教と文化を知る縁(よすが)となる。
聖地はまさに、それぞれの信心に基づく融合と調和、寛容の精神を育む人類共通の巡礼の地となるべきでありましょう。