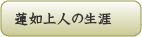
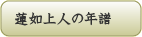
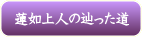
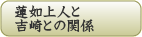
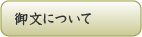
|
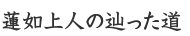
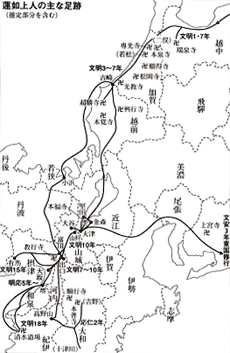
| 応永22年 (1415) |
| |
京都東山の大谷で生まれる
幼名は、「布袋丸」 |
| 文安4年 (1447) |
| |
存如とともに関東に下向 |
| 宝徳元年 (1449) |
| |
存如と北国へ布教 |
| 寛正6年 (1465) |
| 1月8日 |
延暦寺に大谷本願寺を破却されたため、祖像を奉じて近江の金森、堅田、大津を転々とする |
| 応仁2年 (1468) |
| |
北国、東国の親鸞遺跡を訪ねる |
| 文明3年 (1471) |
| 4月上旬 |
大津、三井寺南別所から越前吉崎に赴く。惣村や郷と呼ばれる北陸一帯の自治体に講を結成。その郷民等の力の結集によってそれまで無住であった吉崎山に吉崎御坊を建立。一帯は坊舎や多屋の立ち並ぶ、一大寺内町に変貌した。 |
| 文明4年 (1472) |
| 正月 |
教団が飛躍的な拡大した為、諸山寺に配慮し吉崎を一時閉門 |
| 文明5年 (1473) |
| |
越前の情勢が緊迫。上人は山中温泉に湯治に赴いたり、本願寺末の超勝寺に居を移した後、京都への帰京を試みた。 |
| 文明6年 (1474) |
| |
北陸争乱状態が激しくなる。加越国境地帯で、朝倉・甲斐勢の衝突、また富樫政親が弟の富樫幸千代と合戦を始める。富樫幸千代の加賀に於ける本願寺門徒弾圧に対抗して一向一揆を起こす。 |
| 文明7年 (1475) |
| 8月21日 |
吉崎を退去。小浜、丹波、摂津を経て河内出口に居を定めた。 |
| 文明10年 (1478) |
| |
山科本願寺建立。(堅田源兵衛の殉教事件)御影堂、阿弥陀堂、大門、寝殿など漸次整えられる |
| 文明18年 (1486) |
| |
紀伊に下向 |
| 長享2年 (1488) |
| 5月 |
加賀長享の一向一揆が起こる。以後およそ1世紀にわたって、本願寺門徒が加賀一国を支配する |
| 延徳元年 (1489) 75歳 |
| 5月 |
寺務を五男の実如に譲る。山科南殿に隠居 |
| 明応5年 (1496) |
| 9月 |
大坂石山の地に石山御坊を建立し、居所とした。(後の石山本願寺) |
| 明応8年 (1499) |
| 2月20日 |
死に際し石山御坊より山科本願寺に帰参。 |
| 3月25日 |
山科本願寺において、85歳で入滅する |
|



|